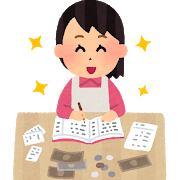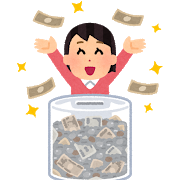ごきげんいかがですか。
むねやんです。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
毎年のこととはいえ、面倒くさいですよね~。
サラリーマンの方は年末調整として会社に丸投げできるんですが、そのわずかな手間ですら面倒くさいと思われるかた、多いんじゃないでしょうか?
ってか、正直、制度の意味と必要性がそもそもよく分からないですよね。
その気持ち、ヒジョーに分かります!

そこで今回は、サラリーマンのための年末調整及び確定申告対策として、用語のおさらいをしようと思います。
「収入と所得の違い」や「扶養控除とは何か?」、など基礎的なことをご説明していきますので、参考にしてみてください。
この辺をきちんと理解して、うまく「節税」できればご家族から賞賛を受けること間違いなしですよー!
※なるべく読みやすいようにシンプルかつ簡単にしましたが、より詳細・正確な情報をお求めの方は専門書や最寄りの税務署等でお調べ下さい。
※所得税と住民税の所得控除額は、正しくは違う数値になりますが、内容が難しくなるのでここでは省略します。正確な数字は国税局・各自治体にお問い合わせください。また法律の随時更新されておりますので、最新の情報をお求めの方も合わせて関係機関にお問い合わせください。
年末調整とは?確定申告とは?
そもそも年末調整とは何のためにするのでしょうか?
日本では収入(所得)によってかかる税金の税率が違います。
毎月の給与で所得税や住民税が引かれていますが、年の途中で結婚したり、子どもが生まれたりと、もろもろの収入や支出の増減によって納税額を調整せねばなりません。
そこで、年末に1年間の所得や個人の生活事情とまとめたうえで再計算することで、納税額の過不足額を調整するものです。
サラリーマンの場合は収入が主に給与収入だけなので、12月の最終給料日までに、その年の収入は確定してしまいます。
その確定情報を把握している会社が、個人に代わって、納税申告を年末(12月最後の支給日まで)ににやってくれます。
だから「年末調整」なんですね。
自営業の方、もしくはサラリーマンだけど給与以外の収入や支出がある人は、それは確定申告として翌年の1/1以降(大体2月中旬~3月中旬)に税務署に報告します。
これは自分でしなくてはいけません。
給与と違い、12/31までどんな収入や支出があるか分からない自営業などの人は、年が明けて前年の支出が完全に確定してから報告するので「確定申告」なんですね。
ここでしっかりと控除の申請をしておくと、年末もしくは翌年に、多く支払い過ぎた税金が還付されるかもしれませんよ。
グラフと用語の説明
「年収」①
収入というのは入ってくるお金、すべてのことです。
基本給はもちろん、残業手当や扶養手当なども含まれます。
1/1~12/31までの収入を指し、税に関しては「収入=年収」と思って差し支えありません。
税金や社会保険料などが差し引かれる前のお金を指すので、「税込年収(ぜいこみねんしゅう)」とも呼びます。
サラリーマンでしたら、月例給与明細と賞与明細の「総支給額」の合計、源泉徴収票の「支払金額」と同じ意味だと思って下さい。
「所得(給与所得・課税所得)」
所得とは、カンタンに言うと収入から「経費・控除」等を差し引いた額になります。
「所得」にはおおまかに2種類あります。
「給与所得」②
自営業の方なら工場の機械代や材料費なんかを「経費」として控除することができますが、サラリーマンは経費を計上できません。しかし経費の代わりに一定額を「給与所得控除」として収入から控除することができます。
この収入から給与所得控除を差し引いた額のことを「給与所得」といいます。
「給与所得控除」は年収によって違います。
また年によって変更もされます。
読むのが面倒な人は「大体65~130万円くらいの人が多い」と思って下さい。
平成29年度 給与所得控除額
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,800,000円以下 | 収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円 ) |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
| 6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
| 10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
「課税所得」
給与所得から社会保険料、生命保険料、配偶者・扶養控除等の各種控除(所得控除。下記で詳しく説明。)を差し引いた額のことです。
例えば、専業主婦の奥さんやお祖父さんお祖母さんと一緒に生活されているかたは給与だけではなかなかやっていけませんよね。
そこで扶養控除なんかで税金の納税額を減らすことができるわけです。
所得税や住民税の額は、この課税所得を元に計算されます。
つまり、ここに至るまでに各種控除を駆使して課税所得をなるべく小さくしておけば、所得税や住民税の額を減らすことができるわけです。
所得控除③
課税所得の項目で少しふれました各種控除のことです。
所得控除には以下のようなものがあります。
控除の種類 控除の概要と所得税計算での控除額 基礎控除 全員一律で適用される控除。この控除は納税者全員に適用されるみんな一律で38万円 配偶者控除 控除対象になる配偶者(夫か妻)がいる場合の控除。基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円) 配偶者特別控除 配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。配偶者の所得に応じて控除額が変わる(最高38万円) 寡婦・寡夫控除 夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除。基本的には27万円(35万円の場合もあり) 扶養控除 控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除。基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる) 勤労学生控除 納税者が勤労学生の場合に受けられる控除27万円 障害者控除 納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除。基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり) 社会保険料控除 社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払った場合の控除その年に支払った金額を全額控除 生命保険料控除 生命保険料を支払った場合の控除、年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円) 地震保険料控除 地震保険料を支払った場合の控除、年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円) 医療費控除 病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%) 雑損控除 災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除損失額に応じて控除額が変わる 小規模企業共済等掛金控除 指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除その年に支払った掛金を全額控除 寄付金控除 寄付をした場合の控除(「ふるさと納税」はこの寄付に当てはまる)特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額。ただし、上限あり(年間所得の40%まで) 青色申告特別控除 青色申告者にだけ適用される特別控除(厳密に言うと、上記してきた所得控除とは位置づけが異なる)10万円 or 65万円
| 住宅借入金等特別控除 | 俗に言う住宅ローン控除。建築・居住年によって違いますが、おおよそ借入額の1%(上限あり)が控除されます。控除期間は10年ほどが一般的です。 |
詳しくは国税局HPをどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
「手取り」
よく所得=手取りと勘違いされる方もおられますが、手取りとは所得から税金を引いた額のことです。
つまり
「手取り」=①収入-②給与所得控除-③所得控除-④所得税・住民税
になります。
つまり、③「控除額」を増やせば、所得が少なくなり、結果、所得をベースに率計算される税金も少なくなるということです。
④所得税・住民税
「所得税」の計算方法については以下の通りです。
読むのが面倒な人は「大体税率10%くらいの人が多い」と思ってください。
所得税計算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「住民税」の内訳は、「所得割」+「均等割」-「調整控除」になります。
それぞれの計算はすこしややこしいですが、ざっくり言うと全部で約10%の税率です。
均等割は自治体によって違いますが、おおよそ5000円ほどですかね。
調整控除額は収入が200万を超えるか超えないか、扶養者の数は何人か等、個人によって違います。
| 税項目 | 所得割 | 均等割 | 調整控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 市区町村民税 | 課税額×6% | ※自治体の額 | ※個人毎の額 | |
| 都道府県民税 | 課税額×4% | ※自治体の額 | ※個人毎の額 |
収入や障害の有無等で非課税になる場合もあります。
詳しくはお住まいの自治体にご確認下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
先ほども説明しましたが、
「手取り」=①収入-②給与所得控除-③所得控除-④所得税・住民税
となりますので、サラリーマンの方は「③所得控除」の額を増やすことで、所得ベースで率計算される④所得税・住民税が減少し、結果最終的な手取りが増えることになります。
年末調整のときに、書類に書き忘れた所得控除はありませんか?
実はお祖父ちゃんお祖母ちゃんを扶養に入れ忘れていたとか、住宅ローン控除が面倒だからやってないとか、そんなことありませんか?
国は税金に厳しいので、わざわざ「申請できてませんよー。」なんて教えてくれません。
ちょっと工夫すれば、法の範囲内で税金の節約は可能です。
年末調整や確定申告で少しでも還付があれば、ちょっと嬉しくなりませんか?
浮いたお金で家族とあったかいものでも食べに行けば、懐だけでなく心も温まること請け合いです。
年末調整の時期も迫ってまいりました。
今からバッチリ準備して、今年最後の大勝負を乗り切りましょーー。おー!
Ate breve! Obrigado!
よろしけば下記の記事もどうぞ
特にiDeCo(確定拠出年金)は、掛金全額が所得控除の対象となりますので、節税・資産形成術としてオススメですよ!
www.munelog-america.com
www.munelog-america.com