
ご機嫌いかがですか。
むねやんです。
さて今回は、前回に続き、年末調整シリーズとして「配偶者控除」をクローズアップしてみたいと思います。

年末調整この時期、むねやんも職場の人から色々と相談を受けることがあります。(何で私!?)
そのときによく話題に上がるのが、「配偶者控除」についてです。
何か「103万円の壁」とか「130万円の壁」とか、ややこしいですよね。数字もよく似てますし。
しかも来年から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の枠が拡大されるので、なおさら混乱しているみたいです。
そこで、今回は「配偶者控除」に関係する情報をざっくりとまとめてみたので、よければ参考にしてみて下さい。
年末調整の概要については、過去の記事をご覧ください。
www.munelog-america.com
※所得税と住民税の所得控除額は、正しくは違う数値になりますが、内容が難しくなるのでここでは省略します。正確な数字をお求めの方、また法律も随時更新されておりますので最新の情報を知りたい方はお近くの税務署・各自治体にお問い合わせください。
「配偶者扶養」とは?
「扶養」というワードはよく聞きますが、実は根拠となる法律や条例、社内規則等によってその意味が違うのはご存じですか?
「扶養」とは主に下記の3つに分けられます。
- 社会保険(健康保険・年金)における扶養
- 支給手当における扶養
- 税控除における扶養
この3つを「扶養」という1つの言葉で簡略化して片付けてしまう事が、年末調整の複雑化や誤解を生む大きな原因であると私は考えています。
①社会保険における扶養
健康保険における扶養
皆様お持ちの健康保険証。
本来、これをもらうためには国民健康保険(第1号被保険者)や社会保険(第2号被保険者)に加入して、保険料を支払わなければなりません。
ただし配偶者の年収が130万円未満の場合、その対となる配偶者(以下、扶養者)の「被扶養者」として申請することができ、その場合の社会保険料は免除(タダ)になります。
年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料を自己負担しなくてはなりません。
なお配偶者が扶養に入っていても外れても、扶養者の社会保険料は変わりません。
ただし、年収が130万円以下の場合でも
- 1日又は1週間の労働時間が正社員の
概ね3/4以上
- 1ヶ月の労働日数が正社員の
概ね3/4以上
の場合は、パートタイマーであっても第2号被保険者になります。
年金における扶養
上記の社会保険料とほぼ同じ条件なのですが、配偶者の収入が年間130万円未満の場合、「国民年金第3号被保険者」に申請することができます。
仮に社会保険(健康保険・年金)の月々の負担額が1.5万円としたら、年間約18~20万円分の節約になりますから、ぜひともやっておきたいですね。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
|---|---|---|
| 20歳以上60歳未満 | 原則65歳未満 | 20歳以上60歳未満 |
| 自営業・無職・学生等、第2号・第3号ではない人 | 厚生年金保険の被保険者と共済組合の組合員 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 保険料は月16,490円(平成29年度) | 厚生年金保険料負担 | 保険料の本人負担なし |
②支給手当における扶養
これは勤務先によりますが、配偶者の収入額によって会社から「扶養手当」を支給してもらえます。
条件は勤務先によって違いますし、そもそも扶養手当自体がない勤務先もありますが、詳しくは勤務先にお問い合わせください。
支給要件は、配偶者の年収額が103万円未満(所得税における扶養と同条件)だったり、130万円以下(社会保険における扶養と同条件)だったりします。
公務員を例にすると、配偶者の扶養手当支給額は8000円(平成30年以降は6500円)ですので、この条件をクリアするかどうかで年間約8万円~10万円分の収入が増えるかどうかに関わってきますので、これもできるなら条件内に収めておきたいですね。
<③税における扶養
ここまでの社会保険・支給手当の扶養に関しては、おおよそ数値が似てますから、「収入130万円以下」さえクリアしていれば、ほぼ全ての扶養条件を満たします。
ここから税における控除の話になりますが、これが非常にややこしくなりますので、少々長くなりますがお付き合いください。
配偶者は無収入?給与収入あり?「配偶者控除」とは?
まず初めに、配偶者が無収入か否か(働いているのかどうか。)で配偶者控除額がどう違うかをまとめます。
配偶者控除の条件
配偶者控除を受けるには、いくつかの条件があります。
図の青色の部分をご覧いただいてから読み進めてみて下さい。

出典:All About 福一 由紀 記
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
上記の「配偶者控除の条件」で注目する項目が(3)です。
配偶者が専業主婦(主夫)の場合は、無収入なので「配偶者控除=38万円」で速やかに解決します。
しかし配偶者がパートなどで収入を得ている場合、給与収入103万円以下の要件を満たしていれば、専業主婦(主夫)と同様、扶養者の給与所得から38万円が控除されます。
また、配偶者の給与所得そのものにも所得税がかかりません。
因みに103万円という数字は、基礎控除38万円に給与所得控除65万円が加わった額を意味します。
| 配偶者項目 | 収入 | 配偶者控除額 | 算定基礎 |
|---|---|---|---|
| 無収入配偶者 | 38万円未満 | 38万円 | 基礎控除38万円 |
| 給与収入配偶者 | 103万円未満 | 38万円 | 基礎控除38万円+給与所得控除65万円 |
となります。
この2つの条件までなら、配偶者控除額は同じということになりますね。
つまり103万円未満までなら、家で家事だけをするよりは外に働きに出た方が家計的には助かるということになります。
(もちろん、それぞれの家庭によって諸事情がありますから、働かなくてはならないというわけではありません。)
あと、ブログや物販での収入は給与ではないのでご注意下さい。
給与収入はいくら?「配偶者特別控除」とは?
次に、配偶者が給与収入を得ている前提として、いくらまでの給与収入ならば配偶者控除が可能なのかを説明します。
図の赤色の部分をご覧になってから読み進めて下さい。

出典:All About 福一 由紀 記
給与収入ありの配偶者控除については上記でご説明しましたが、実は家族のなかで配偶者に限ってのみ、収入103万円を超えても控除できる制度があるのです。
それが「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除の条件
配偶者特別控除を受けるには、いくつかの条件があります。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
「配偶者特別控除」解説
ここでは、配偶者の給与収入額の多さで、配偶者控除額がどう変わっていくのかををまとめます。
上記の「配偶者特別控除の条件」で注目する項目が(ホ)です。
「収入」と「所得」の違いが分かりにくいと思いますが、上記で説明しました通り、この場合は「所得(給与所得)」=「収入(年収)」-「給与所得控除」を意味します。
つまり、
「年間の合計所得金額が38万円超 76万円未満」
||
「年間の合計収入金額が103万円超 141万円未満」
ということになります。
この「年間の合計収入金額が103万円超 141万円未満」に当てはまった場合、配偶者特別控除が適応されます。
控除額は段階的に少なくなっていきますが、他の家族ならば収入103万円を超えた時点で控除額0になるので、少しでも控除されるだけマシだと思って下さい。
配偶者特別控除の控除額(扶養者の合計所得金額900万円以下の場合の場合)
※扶養者の合計所得金額900万円以上の場合は、下記HPを参考にして下さい。
No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
|---|---|
| 103万円を超え105万円未満 | 38万円 |
| 105万円以上110万円未満 | 36万円 |
| 110万円以上115万円未満 | 31万円 |
| 115万円以上120万円未満 | 26万円 |
| 120万円以上125万円未満 | 21万円 |
| 125万円以上130万円未満 | 16万円 |
| 130万円以上135万円未満 | 11万円 |
| 135万円以上140万円未満 | 6万円 |
| 140万円以上141万円未満 | 3万円 |
| 141万円以上 | 0円 |
なお、平成30年1月からは、配偶者控除と配偶者特別控除の要件が変わります。
- 配偶者控除の要件が、年間合計収入金額103万円未満→150万円未満
- 配偶者特別控除の要件が、年間合計収入金額141万円未満→201万円未満
となります。

出典:財務省「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)
各種「〇〇円の壁」まとめ
扶養・控除関係のややこしい「〇〇円の壁」についてまとめてみました。
◆100万円の壁
住民税の非課税枠の要件。
パートなどの給与所得者の住民税には、最低でも基礎控除35万円と給与所得控除65万円がもうけられています。
つまり収入100万円までは課税所得がゼロになり、住民税がかかりません。
◆103万円の壁
配偶者手当(扶養手当)の要件。
勤務先の規則によって違いますが、企業が行う配偶者手当(扶養手当)規則が103万円未満であれば、配偶者手当の支給がなくなります。
給与所得者の所得税の非課税枠の要件。
所得税の基礎控除は38万円、給与所得控除は65万円で、合計103万円までは所得税もかかりません。
扶養者(控除する者)の所得控除の要件
配偶者の収入が103万円までならば、扶養者(控除する者)から配偶者控除38万円を差し引くことができます。
平成30年以降は150万円に拡充されます。
◆106万円の壁
社会保険被扶養(社会保険加入)の要件。
2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上の企業で働く場合は、パートであっても年収106万円以上になると厚生年金と健康保険の加入が義務づけられました。
(ただし1週間の労働時間が20時間以上、勤続年数1年以上という条件付き。学生は適用外)。
この壁を超えると、社会保険の扶養から外れて配偶者自身が社会保険料を負担しなければなりません。
◆130万円の壁
配偶者手当(扶養手当)の要件。
勤務先の規則によって違いますが、企業が行う配偶者手当(扶養手当)規則が130万円未満であれば、配偶者手当の支給がなくなります。
社会保険被扶養(社会保険加入)の要件。
配偶者が従業員500人以下の企業で働く場合、年収130万円以上になると扶養者の社会保険扶養から外れて自分で社会保険料を負担する必要があります。
◆141万円の壁
配偶者特別控除の要件。
配偶者の収入が141万円を超えると、扶養者から差し引ける配偶者特別控除が消滅します。
平成30年以降は201万円に拡充されます。
◆150万円の壁
平成30年1月から施行される、新しい配偶者控除の壁。
配偶者控除が拡大され、従来の配偶者控除の要件が103万円から150万円に引き上げられます。
◆201万円の壁
平成30年1月から施行される、新しい配偶者特別控除の壁。
配偶者控除が拡大され、従来の配偶者控除の要件が141万円から201万円に引き上げられます。

出典:日本経済新聞
総評
いかがでしたでしょうか。
いささか乱暴な説明になってしまった上に、だらだらと長くなってしまいましたが、これが今の自分のプレゼン力の限界です。
結局、配偶者の所得がいくらが一番得なのかという話ですが、これは私の直感ですが、大体、社会保険における扶養の要件額(年収130万円、または106万円)ギリギリまでが一番コスパが良いように思います。
下記HPでシミュレーションをされておられました。
パート収入と手取りの関係と100万・103万・106万・130万・141万円の壁
それによると、収入と手取りの関係は以下のようになるそうです。
A:社会保険料の壁が130万円の場合

B:社会保険料の壁が106万円の場合

水色の部分が、夫の節税分を含めた手取りですね。
Aの場合だと、家計が130万円未満と同じ水準の手取り(夫の配偶者控除含む)をもらおうとしたら、給与収入150万円台後半でやっとトントンになるようです。
時給が同じなら、余分に働くだけ時間がもったいないですよね。
じゃあ130万円未満に抑えた方がよいかと思います。
ただ、社会保険料を納めるということは、それだけ将来の年金額が増えるということですし、「配偶者扶養手当」が絡んでくるとまた手取りも変わってきます。
それは個人個人で事情が違うでしょうから、がんばってご自身でシミュレートしてみて下さい。
少しでも参考になれば幸いです。
これで今年の年末調整もばっちり乗り切りましょー!
Ate breve! Obrigado!
よろしけば下記の記事もどうぞ
特にiDeCo(確定拠出年金)は、掛金全額が所得控除の対象となりますので、節税・資産形成術としてオススメですよ!
www.munelog-america.com
www.munelog-america.com



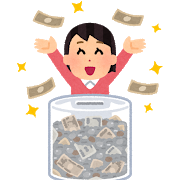


“年末調整もバッチリ節税!配偶者・扶養控除まとめ【103万円:130万円:150万円の壁とは?】” への1件のフィードバック