
ご機嫌いかがですか。
むねやんです。
本日は、一般NISA年間120万円の非課税枠ははたして富裕層の優遇なのかについてお話します。
一般NISAの恒久化見送り
我々投資家の悲願の一つであるNISA恒久化。
それが今年も見送られると先日、政府から発表されました。
政府、与党は16日、期限付きで導入された少額投資非課税制度(NISA)について、恒久化を見送る方針を固めた。恒久化は金融庁や証券業界が求めていたが、現行制度は富裕層への優遇だとの指摘もあり、認めるのは難しいと判断した。
14年に創設されたNISAは株式や投資信託の売却益などが非課税になるのが利点で、年120万円を上限に5年間まで投資できる。今年6月末時点で1161万口座が開設され、一定の支持を集めるが、利用者は裕福な高齢層が多く、短期売買に使われているとの指摘もある。
SsnkeiBiz 2019/10/17
NISAは富裕層優遇の制度?
NISAの恒久化は私としては是非とも進めてもらいたいですが、一方でNISAを恒久化すると抱き合わせで運用課税を20%→25%に引き上げられるのではないかという噂もあるため、ここは少し慎重に行きたいところです。
ただ気になるのは、ここで今回の見送りの理由となった「現行制度は富裕層への優遇だとの指摘」という点です。
誰がこのような見解を出したのかは分かりませんが、むねやんような零細投資家からすれば「年間120万円の非課税枠のどこが富裕層優遇なのか?」と疑問が尽きません。
Twitterの投資クラスタも、これには非難囂々です。
https://t.co/ZXsry7LdtE
年120万枠の投資で富裕層になれるなら苦労しないわ— ピエ~ル (@missingkefkana) October 16, 2019
富裕層からしたらNISAの枠なんてこんなもん。#NISA #恒久化 pic.twitter.com/kM81rhhO7A
— さば (@schwachantoFGO) October 16, 2019
今回はこの辺のについてもう少し掘り下げたいと思います。
年間120万円の投資は高いのか安いのか?
そもそもこの議論、根本的なところは
「年間120万円も生活費以外に拠出できる→富裕層?」
なのかどうかが焦点だと思われます。
確かに、私の周りの投資をしていない家庭が「毎月10万円ずつ貯金してます!」って言ってたら、世帯収入がそれなりにあるか、もしくは家計のやりくりがかなりしっかりしているのかな、という印象を受けます。
ただこれが投資家目線となるとそうでもないんですね。
ネット上の中堅層投資クラスタの意見を見ると、完全もしくは準経済的自立(アーリーリタイア等)を目指している方が多い様に見受けられます。
仮に毎月10万円ずつ投資し、それを年利5%程度で20年運用できた場合、資産は投資資金2400万円に対し資産額は+約1600万円の4074.58万円となります。
運用成績としては十分だとは思いますが、経済的自立の目標額はおおよそ7000万円~1億円前後と言われてますから、これでは少し足りませんね。

投資は元本が大きいほど複利の効果をより受けられます。
投資クラスタが色々と出費を削って少しでも早くより多く投資資金をつぎ込んでいるのはこういう理由があるわけです。
つまり、投資における目標設定を明確にしている投資家、貧困・中間層から富裕層への脱却を目指している投資家にとっては、年間120万円の枠はちょうど良いかもしくは少し少ないものと考えられます。
 むねやん
むねやん 貯金目線なら毎月10万円は高いと思うだろうけど、投資目線なら毎月10万円はちょっと物足りなく感じるわけかぁ。
 はるやん
はるやん 仮に収入が同じだったとしても、立ち位置や見据える先によって捉え方が変わるからな。
富裕層とは
そもそも富裕層とはどういう人々のことを指すのでしょう?
野村総研のレポートでは、おおむね以下のように定義しています。
| 超富裕層 | 5億円以上 |
| 富裕層 | 1億円以上5億円未満 |
| 準富裕層 | 5千万円以上1億円未満 |
| アッパーマス層 | 3千万円以上5千万円未満 |
| マス層 | 3千万円未満 |

 むねやん
むねやん 因みにむねやんはマス層です(´;ω;`)
 はるやん
はるやん 道のりは遠いな。
毎月の投資額(余剰金)について
次に、毎月の投資が毎月10万円というのは適正なのかどうかについて考えます。
今回は、本来貯蓄に回す予定だったお金を投資に使うとしたら、という設定で考察しましょう。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(平成30年)」によると、手取りから貯蓄に回す割合は以下の通りです。
| 手取りから貯蓄に回す割合 | 出現率 |
| 5%未満 | 7.4% |
| 5〜10%未満 | 10.5% |
| 10〜15%未満 | 14.7% |
| 15〜20%未満 | 4.0% |
| 20〜25%未満 | 9.1% |
| 25〜30%未満 | 3.4% |
| 30〜35%未満 | 8.8% |
| 35%以上 | 12.5% |
| 貯蓄せず | 29.7% |
およそ3割近い人が全く貯蓄に回していないというのは驚きですが、それを除けば手取りの約10%~15%を貯蓄に回すのが一般的のようです。
毎月の手取り額が約30万円だとすると、その10%~15%である3万円〜4.5万円ほどが貯金(投資)に回せるということですね。
この割合でいくと、毎月10万円支出するには手取りで月100万円くらい必要になりますね。
 むねやん
むねやん ワーーーオ!?
しかし、次点の貯蓄割合が35%以上ですので、これに当てはめると毎月10万円支出するには手取りで月30万円くらいで大丈夫そうです。
ボーナスがしっかりある会社や夫婦共働きなら何とか達成できるかもしれない金額ですね。
 むねやん
むねやん むねやんもお小遣いを切り詰めて投資に励んでます(´;ω;`)
日本人の平均給与は?
最後に、日本における平均給与の中央値は、国税庁の調査によると以下の通りです。
| 20代 | 約300万円 |
| 30代 | 約410万円 |
| 40代 | 約520万円 |
| 50代 | 約530万円 |
| 60代 | 約380万円 |
これによると、日本人サラリーマンの平均給与は420万円だそうです。
社会保険料等を2割程度引かれるとして、手取りはボーナスを含め月額約28万円になります。
富裕層と庶民の適正投資額は?
上記した「手取りから貯蓄に回す割合」を考慮すると、
| 月額貯蓄率10% → 2.8万円 |
| 月額貯蓄率35% → 9.8万円 |
となります。
月額貯蓄率10%ならばつみたてNISA、月額貯蓄率35%ならば一般NISAの月額投資枠とほぼ同じになりますね。
 むねやん
むねやん こうして計算してみると、一般NISAやつみたてNISAの投資枠ってよく考えられてるんだねぇ。
 はるやん
はるやん 賢い人たちがちゃんと根拠をもって制度を作ってくれてるんだろうな。
一方、富裕層の定義が資産ベースであるため平均年収を調べることができませんでしたが、これを仮に手取り約1000万円だとすると、
| 月額貯蓄率10% → 8.3万円 |
| 月額貯蓄率35% → 29.2万円 |
ということになります。
月額貯蓄率10%の方で一般NISAの年枠120万円とちょうどくらいですが、富裕層になればなるほど家計における生活必需費の割合は下がるので、実際はもっと多くの額を投資に回せる気もします。
ましてやこれが超富裕層ともなると、年枠120万円が生活を圧迫するほどの額とは思えませんし、年120万円分の非課税など微々たるもののように思えます。
結論
手取り年収1000万円は富裕層のかなり低いレベルだとおもいますが、それでも一般NISAの投資枠(年120万円)では余剰資金を持て余すように思えます。
いわんや超富裕層をや!です。
一方、マス層でも普通に貯金すればつみたてNISAの投資枠(年40万円)は可能ですし、お金の管理をしっかりすれば一般NISA(年120万円)の枠を使い切ることもできそうです。
よって、今回のNISA恒久化見送りの理由として挙げた「富裕層への優遇」という見解はおおよそ的外れではないかとむねやんは考えてます。
そもそも一般NISAの意義が中間層の投資熱を上げるためのものでしたし、政府も「これからは年金だけでは老後はやっていけませんよ。」とチクチクぼやいてるのに、やってることが矛盾しているように思えるんですけどね。
まあ先だって年金2000万円問題がありましたから「庶民の味方してます!」アピールなのかもしれませんし、そもそも日本において「投資してる。」ってだけでもう相当のマイノリティですから叩きやすいのかもしれません。
何にせよ、むねやんは富裕層でもないですし、手取りも1000万円には程遠いですが、がんばってお小遣いを切り詰めてつみたてNISAとジュニアNISA、iDeCoの非課税枠を目いっぱい使っていきたいと思います!
 むねやん
むねやん 目指せ!富裕層!
Ate breve! Obrigado!
↓↓本日も応援のポチ、よろしくお願いいたします☆
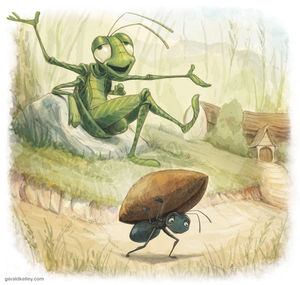



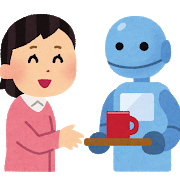
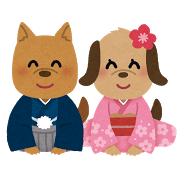
この場合は資産を持ってる=富裕層です。
違う場合の話を持って来ても無意味です。
日本では預貯金も含めた一切の金融資産を持っていない世帯が3割にもなります。
そうした世帯でも消費税を10%超支払っているのに、
投資できるだけの資産を持っている人がその所得税に関して
120万円×5年分=600万円も非課税を設けるのは説明がつきません。
単純に配当利回りを3%とすると18万円の所得が非課税です。
現在多くの高齢者が資産を持っており、ここに課税するために所得税を下げて
消費税を上げています。
その結果低所得者の200万円には10%超の課税、富裕層の18万円には0%の課税
となり、間違っています。
ブロッコリー様
コメントありがとうございます。
>この場合は資産を持ってる=富裕層です。
ブログでも書きましたが、少し私が考えている富裕層の基準とは違うようです。
前提条件が違うのでなんとも返答に困りますが、考え方は色々ありますね。勉強になります。