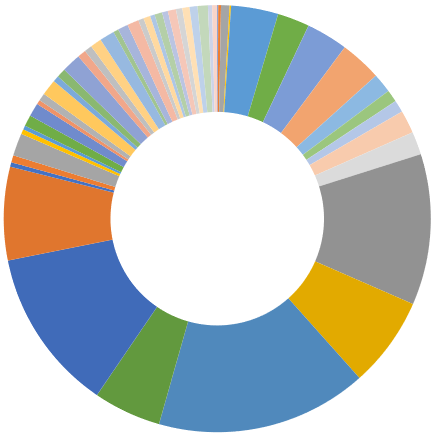ごきげんいかがですか。
むねやんです。
今回は「投資は貯金感覚でできるのか?」というお話です。
投資は貯金感覚?
少し前のことですが、一時期、投資ブロガー界隈で「投資は貯金感覚?」というお題の記事が流行したことがありました。
だれがいつこのような問題提起をしたのか、ネットを中心に調べてみたものの結局分からずじまいでした。
もしかしたら下記の記事がきっかけだったのかもしれませんが、根拠はありません。
ただの私の推測です。
流行からかなり乗り遅れましたが、この件について私の持論を述べさせていただきたいと思います。
(因みに「貯金」とはゆうちょやJAバンクの金融商品のことですが、ここでは貯金も預金も同義として取り扱います。)
投資≠貯金
当然のことですが、投資と貯金は全く違うものです。
貯金とは一般的に「タンス預金」または「普通預金」のことを指します。
預金も厳密には銀行にお金を預けて利子をもらう資産運用の一形態なのですが、感覚としてはほぼ金庫に預けるものと同等です。
つまり貯金とは「将来のためにお金を蓄える行為」であり、「無リスク」かつ「いつでも素早く引き出せる」ものです。
一方、投資とは「利益を得るために財を投じる行為」です。
利益は将来に対する期待であり、確実な成果を生むものではありませんが、運用次第では投じた財を超えるリターンを得ることができます。
この2つ運用方法の最大の違いは2つ。
ひとつは「期待値の有無」つまり「不確実性」が将来のリターンに差を生むということ。
もう一つは、貯金がキャッシュを手元に置いていることに対し、投資はキャッシュを社会に還流させているということです。
投資がオフェンスならば貯金はディフェンス、といったところでしょうか。
どちらが良いことなのかをここで問うのはナンセンスです。
つまりそれくらい、この2つは全く違うことです。
 むねやん
むねやん 投資と貯金は原則、全く違うものだということは覚えておきましょう。
投資⇒貯金感覚には共感
しかし、投資を貯金感覚で行うという思想や感覚については一定の共感を覚えます。
かくいう私も現在、長年コツコツためた「貯金」を「株式」に変換している最中です。
また日々のお小遣いを少しずつ貯めていき、一定額が貯まったら株式を購入しています。
貯金と投資は違うものだと先ほど論じましたが、貯金も投資も私にとっては長期に渡ってコツコツ積み上げていく対象でしかありません。
今まで財形貯蓄に回っていたお金が証券口座に回るようになっただけであり、私がお小遣いとして使えるキャッシュ量は昔と変わりませんので、自分の感覚としては投資を貯金感覚として概念的に捉えることには問題ないと思います。
 むねやん
むねやん 貯金の代わりに資産運用してる感覚でしょうか。
日本人は「貯金」という言葉が好き
それにしても「貯金感覚で投資をする。」とは上手く言うなぁと思います。
投資アレルギーの多い日本人に「投資しませんか?」と呼び掛けても相手にしてもらえないでしょう。
しかしここに「貯金」というワードを加えるだけで、グッと身近なものに感じやすくなるのは我ながら不思議なことだなと思います。
それほど「貯金」は日本人にとって馴染みやすく、また信頼のおけるものなのでしょう。
「貯金」というワードをきっかけに、債券や低コストインデックス投資のような比較的堅実な投資法にビギナーを導くのもアリだとは思いますね。
 むねやん
むねやん 投資をもっと身近なものに感じさせるためのキャッチコピーだね。
「貯金」という言葉に騙されないで
一方で気を付けなくてはいけないことは、「貯金」というワードをエサに高コスト高リスクのボッタクリ商品を売りつけようとする輩がいることです。
私の知り合いに、昔、証券会社に勤めていた方がいます。
彼が言うには、投資信託などの商品を売るときには鉄板の手口があり、
「こちらの商品は、”貯金”みたいなものです。」
というと、今まで頑なに商品購入を断ってきた顧客もコロッと態度を軟化させて買ってしまうことが多いだそうです。
所謂、キラーフレーズというやつでしょうか。
(余談ですが、もうひとつのキラーフレーズは「みんなやってますよ。」なんだそうです。)
こういう手口で、信託報酬や手数料の高い商品を売って営業成績を上げていたんだそうです。
買わせるだけ買わせておいて、その後資産が減ろうが興味はなかったとのこと。
最終的には「投資は自己責任」と言えば一蹴できるんだそうな。
相手も商売でやってますから全面的に非難をするわけにもいきませんが、現在は低コストな優良ファンドもある中、わざわざ高コストな商品を紹介して営業利益に上げてやろうというやり口には辟易します。
そんな風潮が続くから
「投資は危険だ。」
っていうイメージが払拭できずに、いつまでたっても日本の投資熱や金融教育が活発化しないんですよ。
 むねやん
むねやん 貯金という言葉に騙されちゃダメです!
「貯金感覚」は毒にも薬にもなる
こうして改めて考えると、「貯金」という言葉は時と場合によって全く逆の使われ方をしているんですね。
あるときは、「貯金」というワードによって投資のハードルを下げて今まで投資していなかった市民層の参入を促進させる。
一方であるときは、「貯金」というワードによって人々の警戒心を解き、顧客の事を考えないボッタクリ商品を売りつけて投資に対する不信感を募らせる。
同じワードなのに、全く真逆の効果を生んでいます。
結局のところ、投資を貯金感覚でとらえるということは、ある意味では前進的で正しく、またある意味では危険で間違っているとも考えられます。
投資ブロガーさんの間でも意見が分かれたのは、「貯金」ということばをどういう立場から捉えたか、によって解釈が違ったからでしょう。
どちらの意見も正解ですし、「貯金感覚」という言葉の有用性とリスクをちゃんと理解していればどちらの意見を支持しても問題ないかと思います。
まとめ
もし「投資を貯金感覚」として利用したいのであれば、
①投資先をなるべく低コスト・低リスクなものにすること。
②ボラティリティを自分の許容範囲内に収めること。
③いつでも資産を引き上げて現金に戻せること。
④内容が理解できないものには投資しないこと。
⑤欲をかき過ぎないこと。
以上のことを忘れないようにしておけば、騙される確率はずいぶんと下がるのではないでしょうか?
いつかはわざわざ「貯金」なんて言葉を使わなくても、皆が金融リテラシーを高め、誰でもどこでも堂々と投資について議論を重ねられるような社会が来ればよいなぁと願います。
 むねやん
むねやん まずは貯金と貯蓄の違いから理解してみてはどうでしょう?」
Ate breve! Obrigado!
↓↓本日も応援のポチ、よろしくお願いいたします☆
![]()
にほんブログ村
よければこちらの記事もどうぞ
つみたてNISAなら年間上限40万円が非課税なので、初心者でも無理なく始められるのではないでしょうか?
私も一部のお金は防衛資金として普通預金に預けてますよ。
おすすめ普通預金口座はこちら。